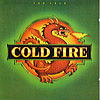
★★ 結構テクニカル |
|
| COLD FIRE (1981) |
| 80年代初頭にたった一枚だけアルバム出した9人編成のコンテンポラリー・ソウルバンド。一曲目の“H,F,R,S,”はシングルになるだけあって今聴くといかにもチャート向けなB級ディスコですが、続く“time
to leave”でのメロウ・ミディアムで柔軟なところを見せてくれ一安心。一枚通して良く聴くとアレンジも結構凝った作りになっていて、キーボードソロもヤルじゃんと思ったらゲスト・クレジットにパトリース・ラッシェンやNDUGU、ネイザン・イーストらの名が。良くありがちな音ではありますがレベルはなかなかなのにこのアルバムだけとは惜しい。 |
|
![]() [A〜C]
[A〜C]