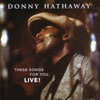
★★★★ 涙モノです |
|
| Donny Hathaway/these songs for you,live! (2004) |
| 名盤「LIVE」からの数曲と、未発表のライヴ音源を含む構成で新たに発表されたアルバム。言わずと知れた「LIVE」はソウル好きによるソウル好きのための…的な内容であったのに対し今回は「someday
we'll all be free」などを含むダニー自身のペンによるメロディアスなナンバーを頭の3曲に持ってきたり、「yesterday」や「superwoman」といった未発表カヴァーなど今の耳で聴いてもまさに「新たなライヴ名盤誕生」と言わざるを得ない。そしてこちらでは歌だけでなくダニーのピアノ・プレイがずいぶんと楽しめる内容となっていて、アーティストとしての彼をあらためて感じさせてくれます。さあ、たまには感動しましょうよ。 |
|
![]() [D〜K]
[D〜K]