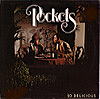
★★ さらにカジュアル |
|
| POCKETS/so delicious (1979) |
| ラストアルバムにあたる本作は音楽性の広さをあえてグッと抑えてダンス&ソウルに統一した感のあるものになっていますが数曲で見せるTOMTOM84を含む全てホーン&ストリングスの入ったゴージャスな作りはそのまま引き継がれています。後半はCharles
Fearingがほとんど曲作りに参加していて、そのせいかギターの効いたナンバーが多く個人的にはこの流れが好きです。Michael
Boddicker,Al McKay,Ed Greeneなど意外とゲストも多彩でしたがEW&Fの弟分から始まり、いろいろと方向性を探ってきたポケッツもこの一枚でついに終了。ブームの終わりを感じるようで寂しいですね。 |
|
![]() [O〜Z]
[O〜Z]