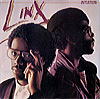
★★ あっさりな黒で |
|
| LINXS/intuision (1981) |
| VO,B,KEY,DS,Gのバンドスタイルをとった軽いブラコン系の音を出すグループですが、実質的にはジャケの二人、特にVOのDavid
Grant中心となっているようです。ピッタリ80年代初頭のブラックといったところで重すぎず黒すぎず、広い層に受けそうな音のカラーが多彩なところはなかなか。特筆はソウル・セッションドラマーとして活躍したオリー・E・ブラウンがプレイだけでなくプロデュースもしている所。そのナンバーはモダンながら一番黒さを感じさせる2曲となっています。他のゲストはNathan
Watts,Paul Jackson.jr,Michael Boddickerなど。 |
|
![]() [L〜N]
[L〜N]